Conference
|
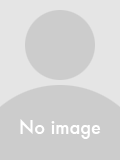
|
Basic information
|
| Name | MIZUTA Tomonori |
| Belonging department | |
| Occupation name | |
| researchmap researcher code | B000219778 |
| researchmap agency | Bukkyo University |
 |
本報告では、東京女学館の英語講師アイリーン・ケーシー(Eileen Mary Casey, 1881-1972年)が暴れ馬を止めた事件の分析を通じ、参政権獲得後のイギリス女性参政権運動家たちの活動について、彼らの「日本観」を踏まえて検討する。
事件は1929年10月28日午後5時半頃、東京府神田区駿河台で発生した。市電の火花に驚いて暴走した馬車を、近くの停留所にいたケーシーが、負傷しながらも取り押さえたのである。行動の理由について、彼女は記者に、「女の身で駄目だと思ったが、イギリスでは最初の発見者の責任であるため飛びついた」と答えている。この事件は、日本の新聞各紙だけでなく、女性自由連盟(WFL)の機関紙 The Vote でも報じられた。
ケーシーはオーストラリアで生まれ、イギリスで活躍した急進的女性参政権論者であった。1911年に女性社会政治同盟(WSPU)に加入し、パンクハーストらとともにロンドンでの「窓破り」などに参加したことで、1913年に逮捕・投獄された経験を持つ。第4次選挙法改正後、彼女は1923-38年を日本で過ごし、日本の女性参政権運動をイギリスに紹介する役目も担った。第二次大戦がはじまるとオーストラリアに移住して検閲局に勤務し、戦後の1951年にイギリスに帰国した。
では、ケーシーたち、イギリスの女性参政権運動家は日本(および日本人女性)をどのように捉えていたのだろうか。運動の機関紙誌に掲載された日本関連記事からみると、当時、主に3つの情報源が「日本観」の形成に影響していた。それは、ジャポニスムを踏まえたイギリス世論の「日本」、日本の政府や留学生が主張した「日本」、そして滞日経験を持つ寄稿者が示した「日本」である。これらの混淆が運動家たちの認識に作用し、ケーシーが戦間期に日本で女子教育に尽力する契機になったと考えられる。
近年の女性参政権運動史研究は、グローバルな視座のもとで、運動をトランスナショナルな結びつきのなかに位置づけ、そこから生まれる多様な「フェミニズムズ」を重層的に描き出す方向に進展している。本報告はこの動向を踏まえ、「たくさんの異なるフェミニズムズの物語」のひとつとして、欧米での「成功体験」を背景に国境を越えた、必ずしも著名ではない実践者が、日本の女性参政権運動に向けたまなざしについて考えてみたい。



