論文
|
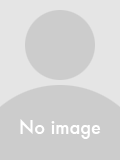
|
基本情報
|
| 氏名 | 小池 伸一 |
| 氏名(カナ) | コイケ シンイチ |
| 氏名(英語) | KOIKE Shinichi |
| 所属 | 【教員用】 通学課程 保医技学部 作業療法学科 |
| 職名 | 教授 |
| researchmap研究者コード | 6000005963 |
| researchmap機関 | 佛教大学 |
 |
目的
医療支援から8年経過した対象(B氏)へのインタビュー調査を行い、A団体の医療支援の効果とB氏に対する国境を越えた作業療法の関わりについて検討すること。
対象と方法
A団体の医療支援を受けドイツに一時移住(渡独)したウズベキスタン共和国在住のB氏を対象に、B氏に対するA団体の医療支援について、A団体のカルテから情報を収集。B氏の帰国後の国際生活機能分類における現在の「心身機能・構造」や「活動」、「参加」などの状況を把握することを目的にインタビュー調査を実施。
結果
B氏はほぼ全ての四肢で拘縮と短縮が認められ、A団体の医療支援により3度渡独し、計8回の入院を行い治療後、退院後はA団体の施設内で作業療法を受けた。医療支援の結果、B氏の身体機能および活動に変化が得られた。3度目の渡独からの帰国直前には屋内での車椅子移動は自立し、食事動作も環境設定を行えば自立していた。帰国時にはA団体職員が保護者に対しドイツでの医療支援の内容と継続すべきリハビリテーション(リハビリ)について情報提供を行った。インタビュー調査から、現在は大学生とビジネスマンとして生活しており、地域行事への参加。日常生活動作は全般に介助を要す。
結論
帰国後に食事動作を含む活動に介助を要することになった要因として、帰国時にB氏の保護者へリハビリに関する内容を含む情報提供が適切に行えていなかったのではないかと考える。国境を越えたリハビリにおいて、対象を含めた関係者のリハビリに対する知識や国境を超える前後での医療環境や社会環境の違いを配慮し、連携する必要があることが示唆



