講演・口頭発表等
|
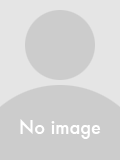
|
基本情報
|
| 氏名 | 濵田 泰彦 |
| 氏名(カナ) | ハマダ ヤスヒコ |
| 氏名(英語) | HAMADA Yasuhiko |
| 所属 | 【教員用】 通学課程 文学部 日本文学科 |
| 職名 | 准教授 |
| researchmap研究者コード | 6000029791 |
| researchmap機関 | 佛教大学 |
 |
勢州山人『北遊記』(半紙本四巻四冊、寛政9・1797年正月刊)は、越中・越後・加賀・能登・佐渡を舞台とした計17話の短編から成る説話作品である。書名の通り、北陸地方全域を覆う地域性の濃厚な説話を蒐集と発信を目的として出版された作品である。また、これも書名の通り、橘南谿『東遊記(正・続)』『西遊記(正・続)』(寛政7~10・1795~1798年刊)の後継となる「諸国奇談集」の流行による出版物でもあることは先行研究によって明らかにされている(木越俊介『知と奇でめぐる近世地誌 名所図会と諸国奇談』2023年、平凡社等)。
しかしながら、実際に生じた出来事を収めたかといえば、一定の注意も要する。たとえば、巻之三の「蛇含草」は、同題の落語でも親しまれた物語である。卵を盗む蛇に一泡吹かせてやろうと木製の卵を飲ませると蛇が苦しみ、蛇含草を口に含むと蛇が回復したのを目撃した主人公が薬用とする本話は、袁枚『子不語』巻二十一「蛇含草消木化金」と一致し、本話は、「蛇含草消木化金」における張文敏の行為を七郎右衛門なる人物に適用した操作がみとめられ、羽咋で実際に起こった出来事や伝説を記録したとは早計に判断できないからである(拙稿「書名「奇談」素描―文事領域拡大の原動力―」『語文』2022年3月)。
加えて、『北遊記』は寛政11(1799)年に刊記のみを改刻した後印本が出版され、さらに序文と章題を改刻した『北陸奇談』と改題して享和3(1803)年に出版される複雑な経緯をたどった。
本発表では、上記の複雑な出版経緯を含め、『北遊記』各編を地方説話の生成と変容という観点から再検討することを目指すものである。



