論文
|
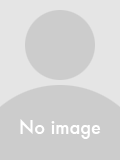
|
基本情報
|
| 氏名 | 李 冬木 |
| 氏名(カナ) | リ トウボク |
| 氏名(英語) | LI Dongmu |
| 所属 | 【教員用】 通学課程 文学部 中国学科 |
| 職名 | 教授 |
| researchmap研究者コード | 1000229759 |
| researchmap機関 | 佛教大学 |
 |
本論は、周樹人が1903年に『浙江潮』誌に発表した初の作品『スパルタの魂』を一つの到達点とし、「スパルタ」知識が「近代」への通路として中国で伝播し、思想の波紋を巻き起こしたプロセスを、知識伝播の観点から初めて探求する。この複雑な流れの中で関連する個人にとって、「スパルタ」は「近代」知識チェーンの一環として、精神史における「近代」への一歩を構成する。本論の主な対象は二名であり、一人は戊戌政変失敗後日本に亡命し、報を通じて歴史に影響を与えた梁啓超、もう一人は当時弘文学院で学ぶ清国留学生周樹人である。近代中国における「スパルタ」伝播チェーンにおいて、彼らは最も重要な担い手であり、知識伝播のプラットフォームである明治日本と最も積極的に相互作用した存在である。本論は、梁啓超の「スパルタ」吸収史を初めて検証し、漸進的な知識蓄積、明治日本との思想的交流、『スパルタ小志』の執筆素材源を含め、彼が中国近代における最も積極的な「スパルタ」導入者かつ最有力な伝播者であることを確認する。これにより、『スパルタ小志』と周樹人およびその『スパルタの魂』の知識・思想上の同形性に関連性が明らかとなる。梁啓超、周樹人、明治日本の知識環境間には、従来の研究視野では見えなかった多重的テキスト交渉の風景が存在する。本論の試みの一つは、上述の新設次元を通じて、過去に触れられなかった問題にアプローチし、従来未解決の疑問を解決することである。『スパルタの魂』が「創作」か「翻訳」かという問題もこの次元内に包含される。キーワード
梁啓超、周樹人、『スパルタ小志』、『スパルタの魂』、明治日本



