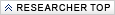Conference
|
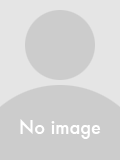
|
Basic information
|
| Name | KOIKE Shinichi |
| Belonging department | |
| Occupation name | |
| researchmap researcher code | 6000005963 |
| researchmap agency | Bukkyo University |
 |
【目的】医療支援を受け母国 に帰国した者に対しインタビューすることで,国際協 力を行う人道援助団体における作業療法士の役割につ いて検討. 【方法】 A団体からの医療支援を受けた経験がある者を対象(B氏)とし た.B氏の渡独していた期間に受けた医療支援に関す る内容および身体機能に関する内容等はA団体のカ ルテより収集した.B氏にオンラインで半構造化イン タビューを実施.内容より逐語録を作成しICFに分類.インタビューで得られた情報とカルテから得た情報に基づき,心身機能, 基本動作,日常生活動作,社会参加の変化を調査.【結果】 B氏は母国においてほぼ全ての四肢で拘縮と短縮が認められ,座位保持が困難な状態であった.3回目の帰国時には 平地での車椅子移動は自立していた.食事動作におい ても環境設定を行えば自立していた.インタビュー調 査にて,現在は大学生とビジネスマンとして生活して いることが分かった.しかしながら,屋内の移動を含 め,日常生活動作は全般に介助を要していた.【考察】 A団体の医療支援はドイツにおける高度な治 療を提供し,B氏に対しICFでの身体機能や活動, 参加の面で効果をもたらした.帰国後の年月を経て子 どもから成人へと成長を遂げた現在,B氏は社会とつ ながりのある生活を送っていた.B氏の母国では早期 に診断および治療を受けることが難しいとされ,障害 者の社会参加が低いことが課題とされている.そのよ うな中でB氏が幼少期に治療を受ける機会が得られ たことは,A団体が実施する医療支援の果たす役割 といえる.また,その中で作業療法士が関わり,車椅 子自走や食事の動作が自立できたことはA団体で活 動する作業療法士の役割であったと考える.一方,B 氏は帰国後に継続すべきリハビリは実施しておらず, かつて行っていた食事動作も介助を要している状況と なっていた.このことは,帰国後の母国におけるリハ ビリテーション環境を含めたドイツと母国の違いが十 分に考慮できていなかったことが原因と考える.国際 協力を行う際,帰国後の母国の文化および環境を配慮 した情報の共有が重要であることが示唆された.今回 は一症例であったため,今後はさらに多くの帰国した 者をフォローアップすることで課題を明確化し,国際 協力においてより充実した作業療法が行えるようにす る必要があると考える