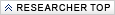Conference
|
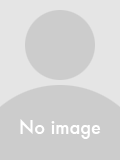
|
Basic information
|
| Name | ONISHI Makiko |
| Belonging department | |
| Occupation name | |
| researchmap researcher code | 5000092698 |
| researchmap agency | Bukkyo University |
 |
中国史上、唯一の女帝となって君臨した則天武后は、易姓革命において仏教的な受命の書として『大雲経』を利用し、登極を果たした。武后は『大雲経』を天下に頒布し、寺ごとに一本を所蔵させて講説させるとともに、諸州に『大雲経』と同じ名称を冠した大雲寺を設置させた。したがって、『大雲経』が武周革命に果たした役割は、きわめて大きなものであったといえる。
この『大雲経』の注疏として、同じく則天武后期に作られたものが、敦煌写本S.2658とS.6502であり、その筆記には則天文字が用いられている。これらはいずれも首尾を欠き題名を失うが、『大雲経』の注疏であること、かつ武后による易姓革命の讖記としての性格が強いことから、『東域伝灯目録』に著録される「大雲経神皇授記義疏一巻」が本来の名称であったと考えられている。『大雲経』が天下諸州に頒布され講じられたことからすれば、この『大雲経神皇授記義疏』も同様に全国に頒たれたはずで、恐らく『大雲経』と一具のものとして書写され、全国の大雲寺に送られたものと考えられる。
さて、同疏が引く『大雲経』について、従来は『大雲経』の現存唯一の訳本である曇無讖訳『大方等無想経』とされ、報告者もこれまでその見解に従ってきた。しかしながら、洛陽・東魏国寺の法明ら十人の僧によって偽撰されたと史書に伝えられる『大雲経』は「四巻」であるのに対し、曇無讖訳は六巻であり、巻数が一致しない。また、経録などの仏教典籍によれば、『大雲経』にはかつて曇無讖訳以外にも複数の訳本が存在していたことが知られる。
そこで本報告では、経録類に記される『大雲経』訳本についての記載を検討したうえで、敦煌写本S.2658とS.6502『大雲経神皇授記義疏』に引かれる経文と曇無讖訳とを比較し、曇無讖訳は本来は竺仏念訳として伝来したものであったと考えられること、さらに同疏に引かれる経文は竺仏念訳を四巻本に縮めたものであったと考えられることを指摘する。